認知症への理解を深める
④ Caring Communityとチームオレンジ
少子高齢化と深刻な介護士不足に直面するドイツでは、介護は大きな社会的課題となっています。現在、要介護者の約9割が在宅で介護を受けており、その半数は家族や友人による介護です。しかし、プロの介護だけでは介護問題を解決できないという認識から、在宅介護の負担を軽減するためにボランティア制度など、さまざまな仕組みが整えられてきました。
一方、大都市ベルリンでは80歳以上の54%が独居世帯であり、家族による介護が担えない世帯が今後さらに増えていくと予測されています。その解決策として近年注目されているのが「Caring Community(Sorgende Gemeinschaft)」です。日本でいえば「地域で支え合おう」という考え方にあたります。
ドイツ語で「Sozialraum」と呼ばれる地域単位で高齢者を見守ることで、当事者ができるだけ長く住み慣れた環境 Lebenswelten で暮らし、社会的孤立や孤独を防ぎ、心身の健康を促す。この仕組みの背景には、介護の専門職は本来の業務に専念でき、市民ボランティアは「社会に貢献したい」という思いを実現できる、という双方のメリットがあります。調査によると、ドイツの団塊世代(1950年代半ば〜1960年代末生まれ)の6割以上がボランティア活動を検討しており、実際に4割強が従事しているそうです。
ただし、介護相談所・医療・地域資源・ボランティアを誰がコーディネートするのかという課題もあり、ドイツではまだモデルプロジェクトの段階にとどまっているのが現状です。それでも、デーヤックは Caring Community がドイツ全土に広がることを心から願っています。
デーヤック友の会では2021年にドイツ10カ所で「チームオレンジ」を立ち上げ、一人暮らしの方や認知症の方を中心に、早期に公的支援制度につなげる体制を築いてきました。認知症の方が自宅で生活する場合、訪問介護や後見制度などの正規の仕組みだけでは十分ではありません。外出時の付き添い、地域のグループ活動の利用促進、さらには、買い物など日常の支援を頼める近隣住民とのつながりが不可欠です。
私たちが日本語で提供できる支援は、地域という大きなネットワークのごく一部にすぎません。しかし、「地域で支える」という発想が社会の常識となるまで、せめて私たちは認知症の日本人の方々にとってのCaring Communityのコーディネーター、すなわちケアマネジャーでありたいと考えています。
Caring Communityはベルリンアルツハイマー協会の専門会議のテーマでした。会議記録(ドイツ語)はこちらをご参照ください。
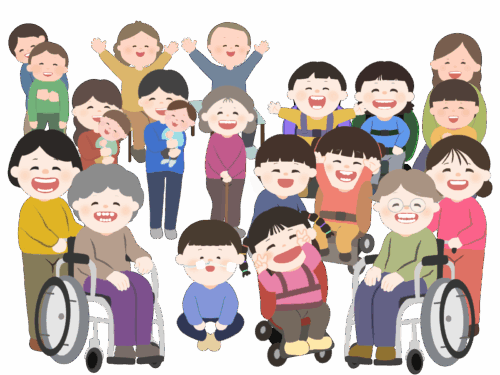
 公益法人
公益法人